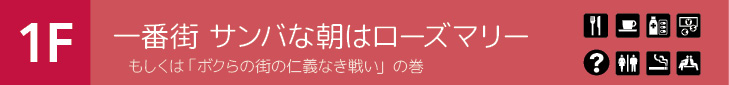
2
パン屋の朝は早い。川野咲紀はいつも通り、六時四十五分にアルバイトとして働いている「ラ・フレイズ」に出勤した。「かたひらアベニュー」の一階にある店舗に入っていく、これまたいつも通り、オーナーであるところの川野康夫――つまり咲紀の父親は、すでに仕込みの真っ最中だった。
いつもより数は少ないながらも、調理室に朝売り用のパンが並んでいるのを確認すると、咲紀はそれらを手早く店頭に並べて、店のオープン準備を整えた。
朝売りのサンドイッチが、なかなかの好評なのだった。「かたひらアベニュー」は、建物の一階部分に、自由通路がある。再開発される前まで、商店街の道路だった部分が、そのまま自由通路として残されたのだ。自由通路を通ると、そのまま方平駅までいける。通勤・通学の人たちは、この自由通路を使うので、その人達を目当てに、朝から販売をしているのだった。
とはいえ、それほど混雑するというほどでもないので、康夫が前日の夜、朝売り用のサンドイッチを仕込み、七時に出勤した咲紀がそれを並べて販売する――というのが、日課となっていた。
しかし、昨晩康夫は組合の理事会に出てたはずで、仕込みができなかったのは、咲紀もわかっていた。だから、朝売りのサンドイッチがないんじゃないかと心配していたのだが……なんとか間に合ったようで、咲紀は胸をなでおろした。が、今朝サンドイッチをつくっていたとなると、いつもの仕込みの時間が短くなるわけで……今日は焼き上がりの時間が遅くなりそうだなと、咲紀は思った。
「そういえば、あれはどうなったの?」
客足が途絶えたのを見計らって、咲紀は調理室に声をかけた。どんなイベントをやるかも気になるけど……それ以上に、「商店街組」と「新規出店組」の争いの行方が気にかかる。
「ああ、あれね……」
力なく、康夫は答えた。一瞬止めた手を、再び動かしながら、康夫は続けた。「どっちもやるんだって」
「へ?」
今度は、咲紀が手を止めた。「なにそれ。理事長がそう言ったの?」
「そう。どっちも甲乙つけがたいんだって。おかげで予算半減だし、企画の手直しで、大変だよ」
康夫の声は、怒りというより疲れがより濃く滲んでいた。
理事会が閉会したあと、康夫をはじめとした「商店街組」は、「かたひらアベニュー」の裏手にある居酒屋に場所を移し、企画の練り直しをしていたのだった。おかげで康夫の帰りは午前様になり、睡眠時間を削られてしまったのである。
「甲乙つけがたいっていうか……どっちもどっちっていうのが、正直なところじゃないの?」
あきれたように、咲紀は言った。「だって、『ご当地アイドル』と『ゆるキャラ』でしょ? どっちもうまくいきそうにないもん」
「相変わらず、咲紀は厳しいなぁ」
と答えたものの、康夫自身も、それを否定できないのだった。
「起死回生のための事業」として、商店街組が提案したのが「かたひらアベニューのご当地アイドルを結成する」で、新規出店組が提案したのが「かたひらアベニューのゆるキャラをつくる」というものだった。どちらも、
「各地で実績のある事業」
と言い張っていたが、行き詰まったあげく、よそがやってることを真似ただけである。
二番煎じどころか、手垢のついたことをやって、はたして起死回生となるのか、咲紀は疑問に思っていたのだった。だからきっと、「どっちもダメ」ということになり、結局いつものセールからくじ引きやらに落ち着くと予想していたのである。
それがまさか、「どっちもやる」という結論になるとは……。
「やると決まったからにはやるしかないんだろうけど、予算半減でどうするのよ」
咲紀が尋ねると、
「それなんだけどさ」
と、康夫が咲紀に近寄ってきた。
もともと、商店街組の計画では、公開オーディションをやって、メンバーを決めて、ライブもやって、正式にデビュー……という青写真を描いていたらしいのだが、そんなことを悠長にやってられる予算はなくなってしまった。なので、手っ取り早く結果を出して、相手の予算をぶんどってしまおう、という結論になったという。
「だから、公開オーディションをやめて、かたひらアベニューでバイトしてる女の子の中からメンバーを選ぶということになったわけ。ほら、『会いにいけるアイドル』って、流行ってるからさ」
「ふーん」
興味もなさそうに、咲紀はトレーを拭き続けている。「会いにいけるっていうのは、そういう意味じゃないと思うけど……」
「そこで、だ」
康夫が言った。「咲紀、アイドルやってみない?」
「はいぃぃぃ!?」
あまりに突飛なことに、咲紀は思わず、手元のトレーを落としてしまった。お客のいない店内に、ガランガランと、トレーの落ちる音が響く。「あ、あ、あたしがアイドル!?」
「お願いします!」
ぱんっと、康夫は手を合わせた。「バイト代、ちゃんと出るからさぁ~」
「バイト代出るって言っても……」
ここでのバイトは、家業の手伝いってこともあり、ほとんどが家計に直行だから、自分の手元にバイト代が残るというのは、咲紀にとって魅力的ではある。「そもそもあたし、二十歳超えてるし!」
短大を出たあと、就職先がみつからずに、家業の手伝いをしている咲紀は、今年で二十一になる。
「大丈夫、プロフィール上は十八ってことにしておくから」
康夫は、ここぞとばかりに拝み倒した。「父さんを助けると思って……お願い!」
土下座せんばかりの勢いに、咲紀は思わずたじろぐ。
そこまで言うなら……バイト代も出るっていうし……と、納得しかけて、咲紀はあわてて首を振る。
「無理に決まってるでしょーが!」
「今日の打ち合わせで話を聞いてから決めればいいからさ」
康夫が言ったところで、タイマーの音が鳴った。「じゃ、頼んだよ」
「ちょっと、そんなこと言われても……」
と言う咲紀の声を無視して、康夫は調理室の奥に、そそくさと引っ込んでしまった。